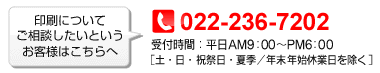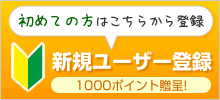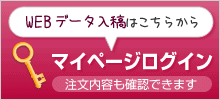日本の近代の暦(カレンダー)その2
2015年10月1日
明治5年(1872)12月3日をもって、明治6年(1873)1月1日とする」
明治政府は明治5年11月9日(西暦1872年12月9日)に改暦詔書を出し、時刻法も従来の1日12辰刻制(1日を12で分けたそれぞれ2時間)から1日24時間の定刻制に替えることを通達しました。
布告から施行までわずか23日というスピード実施です。
しかも12月(師走)がわずか二日で終わってしまったのです!!
当時の人々の混迷ぶりは相当なものでしたでしょう。
今、考えただけでもゾッとします。12月が2日で終ってしかも2ヶ月後にくるはずの正月が3日後にくるんですから!
従来の年中行事や慣習がめちゃくちゃにたったのはゆうまでもありませんね。
なぜこれほどのスピード実施になったのかというと、明治政府の財政危機があったといいます。
翌年の明治6年は旧暦で閏月があり1年が13カ月になり、官吏(当時の官公庁や軍の方々をそうよびます)の給料を13回支払わなければなりません。
出費がかさむ、いっそ太陽暦を採用すればその心配もなくなり、その上、明治五年の12月も2日しかなければ、12月の給料までもまるまる節約できると考えたのです。
これがスピード改暦の真相だったとか。ずいぶんと明治政府は無茶をしましたね。
むろん表向きは、欧米に追いつけ追い越せ、富国強兵が急務だった日本は、日本暦と西洋暦との間で起こる暦のズレは深刻な問題だったので、まあ早かれ遅かれこうなっていたのでしょう。必然の流れですね。
約1000年以上も太陰太陽暦を使ってきた日本。今の暦になって150年ほど、カレンダーには旧暦が載っているものもあります。日本の近代の暦のおいたちを知ってみるとなんだか奥深いものになるのではないでしょうか。